2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正省令が施行され、職場における熱中症対策が義務化されました。
全国の職場での熱中症による死傷者は、去年、統計を取り始めてから最も多い1257人に上りました。
このうち亡くなった人は31人で、3年連続で30人以上となっています。
厚生労働省がおととしまでの4年間で、職場で死亡した合わせて103人を分析したところ、9割を超える100人は初期症状の放置や対応の遅れが死亡に至った原因だったということです。

この熱中症対策義務化は、条件を満たす作業を行う企業は全てが対象です。
対策を怠った場合には罰則があるため、多くの企業で社内の熱中症対策を見直す必要があります。
では、義務化の背景、対策は具体的にどうしたらいいのか、そして企業の対応手順について解説していきます。
●熱中症対策の義務化の背景
- 地球温暖化の影響による熱中症リスクの増加
- 職場における熱中症による死傷者数の増加
上記2点が挙げられますが、過去数年間の熱中症による死亡災害のうち、100件は「重篤化した状態で発見される」「医療機関に搬送しない」などの初期症状の放置や対応の遅れが原因と言われています。
●熱中症対策が義務付けられる作業の条件とは
熱中症対策はすべての企業で義務付けられるわけではなく、一定の条件を満たす作業を実施する企業において義務化されます。
義務付けられる作業の条件
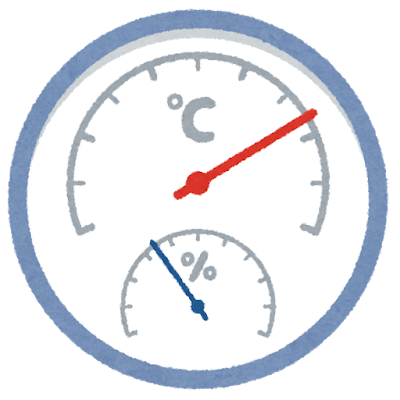
- WBGT(暑さ指数)28度以上の環境
- 気温31度以上の環境
求められる対策
上記の作業を行う企業は
①報告体制の整備
②実施手順の作成
③関係者(労働者)に周知
を行う必要がある
対策を怠った場合の罰則
6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性がある
●そもそもWBGT値ってなに?基準値は?
WBGTは、熱中症のリスクを示す指標のことで「暑さ指数」とも呼ばれています。
気温だけでなく、湿度や輻射熱(地面や建物からの照り返しなど)も考慮されて計算され、より人体が感じる暑さに近い指標とされています。

WBGT値が基準値を超えると熱中症のリスクが高まると言われ、環境省の熱中症予防情報サイトにおける「暑さ指数(WBGT)の実況と予測」を参考にすることが可能です。
しかし、公表内容はあくまで地域を代表する一般的な値であり、個々の作業場所や作業ごとの状況は反映されていないため、WBGT測定器を設置して、それぞれの場所を計測しましょう。
作業環境の条件はどのくらい当てはまる?
作業強度や着衣の状況などによっては、上記の作業に当てはまらない場合でも熱中症のリスクが高まります。
そのため厚生労働省は、以下の表に基づいて、身体作業強度(代謝率レベル)とWBGT基準値を比較することを推奨しています。

出典:職場における熱中症対策の強化について
WBGT基準値を超える場合には、冷房の活用や作業内容・作業場所の変更などにより、低減を図りましょう。
熱中症対策義務化の対象となりそうな業種は?
今回の改正省令では、熱中症対策を義務づける職種・業種などは定めていません。
上記の条件に当てはまる作業をおこなう企業は全てが対象となり、作業内容が屋内か、屋外かなども問われません。
そのため、建設業や警備業などの屋外作業が多い業種だけでなく、工場や倉庫での作業を中心とする業種も場合によっては対象となるでしょう。
そのほか、外回りが多い営業職なども、気温31度を超える日に1時間以上出歩く場合は対象となります。
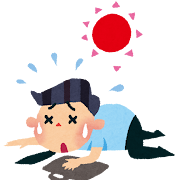
このように、幅広い業種が熱中症対策義務化の対象となるため、事業者はいま一度、自社が該当しないか業務内容を確認しましょう。
6月から企業に求められる熱中症対策
熱中症対応の基本的な考え方は、見つける→判断する→対処するです。
そのためにも、熱中症対策をしなければならない企業においては「①報告体制の整備」「②実施手順の作成」「③関係者(労働者)に周知」が義務づけられます。
1. 報告体制の整備(見つける)

熱中症の被害を拡大させないためには、早期発見が不可欠です。
以下の報告体制の整備をおこない、労働者だけでなく、熱中症のおそれのある作業に従事する労働者以外の者も含むすべての関係者に周知する必要があります。
- 「熱中症の自覚症状がある労働者」がその旨を報告するための体制
- 「熱中症のおそれがある労働者を見つけた者」がその旨を報告するための体制
熱中症が疑われる症状としては、めまいや頭痛、吐き気、倦怠感などが挙げられます。
労働者自身にこのような自覚症状がなくても、大量に汗をかいている、ふらついている、ぼーっとしているなど、普段と様子が違う労働者を見つけたら熱中症を疑いましょう。
下記などの取り組みを実施することで、熱中症のおそれがある労働者などを早期発見・把握することができます。
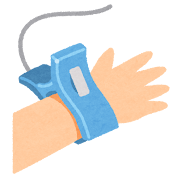
- 職場巡視…作業現場を定期的に見回り、労働者の状態を確認する
- バディ制の採用…2人1組などで作業をおこない、お互いの体調に気を配る
- ウェアラブルデバイス等の活用…体温や心拍数などを測定できる機器を利用する
- 定期連絡…現場と管理者の間で定期的に連絡を取り合い、異常がないか確認する
2. 実施手順の作成(判断する)
熱中症の疑いがある労働者を把握した場合、迅速かつ的確な判断をおこない、重篤化を防ぐために必要な措置を講じることも企業の義務です。

いざという時に的確な判断ができるよう、事業場ごとに、緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先および所在地などを関係者に周知し、以下の措置の実施手順をあらかじめ定めておきましょう。
実施手順を作成すべき措置の内容
- 作業からの離脱(暑熱な場所での作業を中断させる)
- 身体の冷却(体を冷やす)
- 水分・塩分の摂取(意識がある場合はすぐに摂取させる)
- 必要に応じた医療機関への搬送(医師の診察または処置を受けさせる)
- 経過観察 (措置をとっている間の対応)
- 緊急連絡網の活用(必要な関係者〈家族・医療機関など〉に連絡する)
実施手順については、現場の実態に即した具体的な手順を作成することが求められています。
3. 関係者に周知(対処する)

熱中症は体調や持病によっても影響を受けるため、労働者だけでなく、熱中症のおそれのある作業に従事する全ての関係者への周知が必要です。
朝礼やミーティング、社内メール、社内掲示板などを活用し、熱中症対策の周知に努めましょう。
【参考】職場における熱中症対策の強化について
効果的な職場における熱中症対策事例
厚生労働省が公表している「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」実施要綱などでは、義務化される措置以外にも、効果的な熱中対策が多数挙げられており、これらも参考にしつつ総合的な取り組みを進めていくことをオススメします。
作業環境の管理
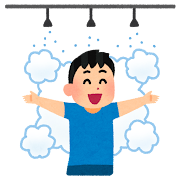
WBGT値を低減するための対策(簡易な屋根の設置、通風・冷房設備の設置、ミストシャワー等による散水設備の設置など)をする
作業時間の短縮

長めの休憩時間を設定したり、WBGT値が基準値を大幅に上回る場合は、原則として作業を控える
暑熱順化への対応
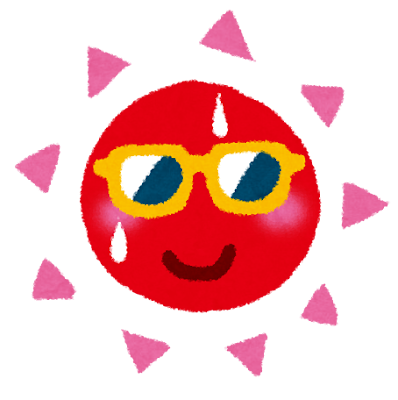
暑さに慣れていない人(暑熱非順化者)は熱中症リスクが高いため、作業時間を調整しながら、徐々に暑さに慣れさせる(暑熱順化)
計画的な暑熱順化プログラムを組む
(暑熱順化が進むと、同じ暑さでも熱中症になりにくくなる)
水分や塩分の摂取

のどが渇いたと感じる前に、作業前後に加えて、作業中も定期的に水分と塩分を摂取することが求められる
管理者は、摂取状況を確認したり、水分を常備したり、休憩設備を工夫したり、塩飴や飲料水の備え付けなどして、労働者の摂取を徹底させる
熱中症予防管理者の設置

熱中症予防適切な対策に取り組むための責任者として、十分な知識を有する者の中で熱中症予防管理者を選任し、現場担当者と連携して取り組むことが推奨されている
服装の調整

熱を吸収・保熱しにくく、透湿性および通気性の良い服装を準備する
日光下での作業には、通気性の良い帽子やヘルメットなども有効
プレクーリング
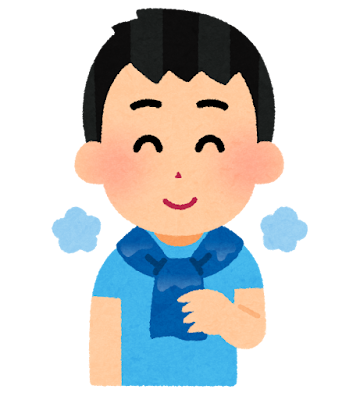
作業開始前や休憩時間中に身体を冷やすことで熱中症のリスクを軽減する
健康管理

疾患がある労働者への配慮や、日常的な健康管理に関する指導、作業開始前や作業中の健康状態など確認を行う
会社も対策をしつつ、個人でも対策を!
これは、最近の猛暑による熱中症労働災害の増加、特に初期症状の放置や対応の遅れによる重篤化を防ぐための重要な法改正です。
人事・労務担当者は、自社の作業環境を特定し、熱中症リスクを評価した上で、報告体制や対応手順を具体的に整備し、文書化することが急務です。
個々人でも熱中症にならないための対策や、少しでも体調がおかしいと思ったらすぐに誰かに報告するなど、危機感をもって行動するようにしましょう!
また、熱中症に対する補償などについては、ぜひ弊社にご相談ください!
個人の熱中症対策などについてはこちらをクリック!
公式LINEアカウントが出来ました!
/カテゴリ: お知らせ, 情報みなさまからよくお問い合わせをいただいておりました、
弊社LINEアカウントをついに作成しました!
お問い合わせや相談予約などのコメントを送っていただくと、
LINEから対応させていただきます。
また、不定期にはなりますが、お役立ち情報を配信していく予定です!
ぜひお友達追加をお願いします☆彡
下記画像をクリックしていただくと登録画面に飛びます!
その他、QRコードを読み取るか、ID検索でも登録できます♪
また、これを機に、メルマガ配信を停止する運びとなりました。
今までメルマガにご登録いただいておりましたお客様におかれましては、
お手数ですが、LINEに登録しなおしていただければ幸いです。
たくさん利用していただけると嬉しいです!
よろしくお願いいたします♪
【Teamがん対策ひろしま】尾道開催 講演会のお知らせ
/カテゴリ: お知らせ, スタッフのつぶやき「乳腺疾患患者の会 のぞみの会」様が、尾道にて講演会を開催されます。
弊社もTeamがん対策ひろしまの登録企業として、こちらの後援会を支援しております。
参加費は無料ですのでぜひご参加ください!
詳しくは下記詳細をご覧ください。
他人事ではない!熱中症対策!
/カテゴリ: 情報2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正省令が施行され、職場における熱中症対策が義務化されました。
全国の職場での熱中症による死傷者は、去年、統計を取り始めてから最も多い1257人に上りました。
このうち亡くなった人は31人で、3年連続で30人以上となっています。
厚生労働省がおととしまでの4年間で、職場で死亡した合わせて103人を分析したところ、9割を超える100人は初期症状の放置や対応の遅れが死亡に至った原因だったということです。
この熱中症対策義務化は、条件を満たす作業を行う企業は全てが対象です。
対策を怠った場合には罰則があるため、多くの企業で社内の熱中症対策を見直す必要があります。
では、義務化の背景、対策は具体的にどうしたらいいのか、そして企業の対応手順について解説していきます。
●熱中症対策の義務化の背景
上記2点が挙げられますが、過去数年間の熱中症による死亡災害のうち、100件は「重篤化した状態で発見される」「医療機関に搬送しない」などの初期症状の放置や対応の遅れが原因と言われています。
●熱中症対策が義務付けられる作業の条件とは
熱中症対策はすべての企業で義務付けられるわけではなく、一定の条件を満たす作業を実施する企業において義務化されます。
義務付けられる作業の条件
求められる対策
上記の作業を行う企業は
①報告体制の整備
②実施手順の作成
③関係者(労働者)に周知
を行う必要がある
対策を怠った場合の罰則
6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性がある
●そもそもWBGT値ってなに?基準値は?
WBGTは、熱中症のリスクを示す指標のことで「暑さ指数」とも呼ばれています。
気温だけでなく、湿度や輻射熱(地面や建物からの照り返しなど)も考慮されて計算され、より人体が感じる暑さに近い指標とされています。
WBGT値が基準値を超えると熱中症のリスクが高まると言われ、環境省の熱中症予防情報サイトにおける「暑さ指数(WBGT)の実況と予測」を参考にすることが可能です。
しかし、公表内容はあくまで地域を代表する一般的な値であり、個々の作業場所や作業ごとの状況は反映されていないため、WBGT測定器を設置して、それぞれの場所を計測しましょう。
作業環境の条件はどのくらい当てはまる?
作業強度や着衣の状況などによっては、上記の作業に当てはまらない場合でも熱中症のリスクが高まります。
そのため厚生労働省は、以下の表に基づいて、身体作業強度(代謝率レベル)とWBGT基準値を比較することを推奨しています。
出典:職場における熱中症対策の強化について
WBGT基準値を超える場合には、冷房の活用や作業内容・作業場所の変更などにより、低減を図りましょう。
熱中症対策義務化の対象となりそうな業種は?
今回の改正省令では、熱中症対策を義務づける職種・業種などは定めていません。
上記の条件に当てはまる作業をおこなう企業は全てが対象となり、作業内容が屋内か、屋外かなども問われません。
そのため、建設業や警備業などの屋外作業が多い業種だけでなく、工場や倉庫での作業を中心とする業種も場合によっては対象となるでしょう。
そのほか、外回りが多い営業職なども、気温31度を超える日に1時間以上出歩く場合は対象となります。
このように、幅広い業種が熱中症対策義務化の対象となるため、事業者はいま一度、自社が該当しないか業務内容を確認しましょう。
6月から企業に求められる熱中症対策
熱中症対応の基本的な考え方は、見つける→判断する→対処するです。
そのためにも、熱中症対策をしなければならない企業においては「①報告体制の整備」「②実施手順の作成」「③関係者(労働者)に周知」が義務づけられます。
1. 報告体制の整備(見つける)
熱中症の被害を拡大させないためには、早期発見が不可欠です。
以下の報告体制の整備をおこない、労働者だけでなく、熱中症のおそれのある作業に従事する労働者以外の者も含むすべての関係者に周知する必要があります。
熱中症が疑われる症状としては、めまいや頭痛、吐き気、倦怠感などが挙げられます。
労働者自身にこのような自覚症状がなくても、大量に汗をかいている、ふらついている、ぼーっとしているなど、普段と様子が違う労働者を見つけたら熱中症を疑いましょう。
下記などの取り組みを実施することで、熱中症のおそれがある労働者などを早期発見・把握することができます。
2. 実施手順の作成(判断する)
熱中症の疑いがある労働者を把握した場合、迅速かつ的確な判断をおこない、重篤化を防ぐために必要な措置を講じることも企業の義務です。
いざという時に的確な判断ができるよう、事業場ごとに、緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先および所在地などを関係者に周知し、以下の措置の実施手順をあらかじめ定めておきましょう。
実施手順を作成すべき措置の内容
実施手順については、現場の実態に即した具体的な手順を作成することが求められています。
3. 関係者に周知(対処する)
熱中症は体調や持病によっても影響を受けるため、労働者だけでなく、熱中症のおそれのある作業に従事する全ての関係者への周知が必要です。
朝礼やミーティング、社内メール、社内掲示板などを活用し、熱中症対策の周知に努めましょう。
【参考】職場における熱中症対策の強化について
効果的な職場における熱中症対策事例
厚生労働省が公表している「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」実施要綱などでは、義務化される措置以外にも、効果的な熱中対策が多数挙げられており、これらも参考にしつつ総合的な取り組みを進めていくことをオススメします。
作業環境の管理
WBGT値を低減するための対策(簡易な屋根の設置、通風・冷房設備の設置、ミストシャワー等による散水設備の設置など)をする
作業時間の短縮
長めの休憩時間を設定したり、WBGT値が基準値を大幅に上回る場合は、原則として作業を控える
暑熱順化への対応
暑さに慣れていない人(暑熱非順化者)は熱中症リスクが高いため、作業時間を調整しながら、徐々に暑さに慣れさせる(暑熱順化)
計画的な暑熱順化プログラムを組む
(暑熱順化が進むと、同じ暑さでも熱中症になりにくくなる)
水分や塩分の摂取
のどが渇いたと感じる前に、作業前後に加えて、作業中も定期的に水分と塩分を摂取することが求められる
管理者は、摂取状況を確認したり、水分を常備したり、休憩設備を工夫したり、塩飴や飲料水の備え付けなどして、労働者の摂取を徹底させる
熱中症予防管理者の設置
熱中症予防適切な対策に取り組むための責任者として、十分な知識を有する者の中で熱中症予防管理者を選任し、現場担当者と連携して取り組むことが推奨されている
服装の調整
熱を吸収・保熱しにくく、透湿性および通気性の良い服装を準備する
日光下での作業には、通気性の良い帽子やヘルメットなども有効
プレクーリング
作業開始前や休憩時間中に身体を冷やすことで熱中症のリスクを軽減する
健康管理
疾患がある労働者への配慮や、日常的な健康管理に関する指導、作業開始前や作業中の健康状態など確認を行う
会社も対策をしつつ、個人でも対策を!
これは、最近の猛暑による熱中症労働災害の増加、特に初期症状の放置や対応の遅れによる重篤化を防ぐための重要な法改正です。
人事・労務担当者は、自社の作業環境を特定し、熱中症リスクを評価した上で、報告体制や対応手順を具体的に整備し、文書化することが急務です。
個々人でも熱中症にならないための対策や、少しでも体調がおかしいと思ったらすぐに誰かに報告するなど、危機感をもって行動するようにしましょう!
また、熱中症に対する補償などについては、ぜひ弊社にご相談ください!
個人の熱中症対策などについてはこちらをクリック!
【Teamがん対策ひろしま】がん患者支援団体のイベントお手伝いをしてきました
/カテゴリ: お知らせ, スタッフのつぶやき2024年より、Teamがん対策ひろしまの登録企業として活動している弊社ですが、
5月17日・18日に行われた福山ばら祭りで、
「乳がん患者会 福山アンダンテ」様の出店に伴いお手伝いとして参加してまいりました。
福山アンダンテ様は、乳がんを経験した方ががん検診の啓発活動や、がんに関する情報提供を行われているボランティア団体です。
ばら祭では、乳がんのシリコンモデルを使って、実際に乳がんのしこりがどんなものなのかを来場者に体験していただいたり、がん検診の大切さや、自己検診の仕方などを説明しました。
弊社としても、がんの知識は日々更新していっておりますので、情報提供をしてまいりました。
(ピンクのリボンで編んだ帽子はアンダンテの皆様の手作りで、ご来場の方からもかわいいと好評でした♪)
がんは早期発見すれば治る病気です。
ぜひ、自分のために、家族のために、がん検診は年に1回受けましょう!!
また、医療の進歩にともない、がん保険も進化していっています。
がんが見つかったら、お金の心配をしないで様々な治療ができるよう、がん保険の見直しもしましょう!!
デジタル資産の万が一にそなえていますか?
/カテゴリ: 情報朝晩がすこし肌寒かったり、日中は汗ばんだりする季節になりました。
福山ではばら祭りが開催され、ばらもきれいに咲き誇っていましたね!
さて、今日は「デジタル資産」のお話です。
みなさんは、「デジタル資産」と聞いて、なにを思い浮かべますか?
●デジタル資産とは
上記のとおり、様々なものがデジタル資産とされています。
最近では、証券口座が不正にアクセスされ、多額の株が購入されてしまうという事件が多数発生しています。
☆「スマートフォン内の個人情報(アドレス帳、写真、動画)」
男女ともに幅広い年代の人が保有しており、特に40代では、男女ともに50%を超えています。
☆銀行のWeb口座やネット証券、仮想通貨などのオンライン上の金融資産
比較的女性よりも男性のほうが保有率が高い傾向にあるようです。
●証券口座不正アクセスの手口
以前から証券会社のフィッシングサイト(偽サイト)は確認されていましたが、主な目的は個人情報の転売と見られていました。
しかし、最近は口座乗っ取りで特定の個別株を大量に購入する新たな手口。
悪用者は株価をつり上げたところであらかじめ保有する株を売却し、利益を得ていると見られています。
きっかけは…
新NISA(少額投資非課税制度)によってネット証券口座を開設する人が急増しているのも狙われやすくなったきっかけになっているかもしれません。
操作に慣れていなかったり、購入後に口座を放置してしまったりすると、フィッシングメールなどに驚き、だまされてしまうケースがあるということです。
フィッシングサイトの流入経路
フィッシングサイトの流入経路はSMSかフィッシングメールの2つ。
「このままだとロスカット(強制決済)に」などとユーザーの不安をあおり、ログインするように仕向けています。
URLをクリックすると本物そっくりの証券サイトのログイン画面が表示され、IDやパスワードなどを入力してしまうと、情報が盗み取られる仕組みだそうです。
最近ではIDとパスワードのみならず、SMSなどで送られた認証パスコードを使った2段階認証まで突破する「リアルタイムフィッシング」詐欺も横行しているとか。
その流れとしては…
ユーザーがフィッシングサイトにIDやパスワードを入力
↓
「確認中」「Loading」といった画面が表示(待機中のユーザーは、本物のサイトにログインしたものと勘違い)
↓
その間に悪用者は盗んだ情報を基に本物のサイトにログイン
↓
2段階認証に必要な認証パスコードがユーザーのSMSやメールに送信される
↓
ユーザーがフィッシングサイトに入力すると、悪用者はそれを盗み、2段階認証を突破
本当に巧妙にできています。
●不正アクセスへの対策
証券口座乗っ取りは複数の詐欺グループによる「分業」で実現していると見られています。
そのため、犯人の特定は難しいのが実情です。
日本証券業協会は証券各社に多要素認証の設定を必須にするよう呼びかけています。
ですが、いつから必須とするかは個社の判断に委ねられているため、ユーザーは証券会社に頼るのみならず、自分でも対策を講じる必要があります。
自分でできる対策とは
といった行動を心がけるのが、フィッシングサイトにひっかからない方法です。
地震などの防災対策はしっかりされている人は多くなっていますが、デジタル資産の防災対策をしている人は20%にも満たないと言われています。
顧客の落ち度によって、補償に差が出る事例もあるようなので、早めの対策をして万が一の対策に備えましょう。
●デジタル遺産・デジタル遺品
さて、「遺産」と聞くと、土地・建物などの不動産や宝石、預貯金通帳などをイメージする人が多いと思います
しかし、様々な場面でデジタル化が進む現代においては、故人がデジタル形式で保管していた財産も遺産に含まれます。
デジタル遺産は以下の通りに分けられます。
◎一般的に金銭に関する財産
◎そうではない財産
金銭に関する財産
ネット銀行やネット証券の口座、FX、仮想通貨といった金融資産、電子マネーの利用残高や商品を購入できる各種ポイント、マイレージのほか、デジタルの著作物(著作権)も含まれる
金銭に関しない財産
デジタル遺品と呼ばれ、デジタル機器本体やインターネット上に保存された情報など。
例えば、スマートフォンに保存された写真や動画、インターネット上に保存された各種クラウドデータ、SNSサービスのアカウント、連絡先、個人ブログの情報など
ここでは、相続や贈与に係るデジタル遺産の取り扱いについて説明します。
●デジタル遺産への対策も忘れずに
本人にしかわからない…!
デジタル遺産は、デジタル上にあり、本人にしかわからない情報で管理されているため、相続人がその存在に気づかないことも想定されます。
また、その存在を認識していた場合でも、インターネット上のアカウントは、本人が設定したIDやパスワードなどで保護されており、IDやパスワードがわからない場合はアクセスすることができません。
顔認証や指紋認証、2段階認証といった複雑な設定をされている場合も同様です。
さらに、故人が音楽や動画、オンラインサロンなどの有料サービスを定額利用(サブスクリプション)契約していた場合は解約されないまま課金が継続されるため、注意が必要です。
デジタル遺産の相続時においては、名義変更や解約など、オンライン上で手続きを完結しなければならないケースが多く、相続人に相応のITリテラシーが求められます。
相続人が気付かなかったら…
相続人がデジタル遺産に気づかず、相続手続きを済ませてしまった場合、事後に遺産分割協議のやり直しや期限後申告、修正申告となり、相続トラブルに発展するケースもあり得ます。
きちんと生前整理を
デジタル遺産を所有している人は、相続人がその存在を把握できるよう、生前整理をしておくことが大切です。
エンディングノートやスマートフォンなどで入力できる終活アプリに、デジタル遺産の内容やアクセス方法、処分方法を記録し、家族と共有しておくことをお薦めします。
相続手続きまでを念頭に置くと、デジタル遺産は遺言書の形で残すことが望ましいです。
また、第三者によるアカウントの乗っ取りやなりすましを防ぐためにも、死後委任契約などで代理人に管理を依頼する方法もあります。
●便利な世の中、落とし穴がある?
このように、デジタルで管理できるものが増えてきていますが、その分詐欺集団に狙われやすくなったり、相続で困ったり、ということが起き得ます。
自分のためにも、遺された人のためにも、対策は早めに必ずしておきましょう!!
【Teamがん対策ひろしま】ばら祭りでお手伝いしてきます
/カテゴリ: お知らせ, スタッフのつぶやき来る5月17日・18日は、福山ばら祭りが開催されます!
弊社も「乳がん患者会 福山アンダンテ」様のお手伝いをしてまいります。
乳がんモデルで実際に乳がんがどのようなしこりなのか、体験してみませんか?
ぜひ、ご来場おまちしております!!
4月から色々と変わっています!
/カテゴリ: 情報物価上昇が止まらず、3月31日にティッシュを買った!という話もちらほら聞きましたが、物価に関わらず、4月から色々と変更したことがありますので、今回はいくつかピックアップしてお届けします!
仕事と育児・介護の両立
育児・介護休業法が改正され、育児の分野では、子どもの看護休暇についてけがや病気のほか、入園式や卒園式、入学式、感染症に伴う学級閉鎖などでも取得できるようになります。
対象も「小学3年生修了」までに広がります。
4月の改正では、3歳以上小学校就学前の子どもを持つ親の残業免除の対象拡大や、行事参加のための子の看護休暇の取得が可能になります。
また、従業員300人超の企業には育児休業取得状況の公表が義務化され、介護離職防止のための支援も強化されます。
10月には、働き方の柔軟化措置が新設され、企業は妊娠・出産の申し出を受けた際に、仕事と育児の両立に関する意向を確認し、配慮することが義務化されます。
育児や介護と仕事を両立しやすい環境が整備されることが期待されます。
一方、介護の分野です。
企業の義務となるのは、
●介護に直面したと申し出た人に介護休業の制度などを周知し、それを利用するか個別に意向を確認すること
●介護保険料の支払いが始まる40歳の従業員を対象に仕事と介護の両立に向けた情報を提供すること
です。
さらに、3歳未満の子どもを育てる人や要介護状態の家族を介護する人がテレワークを選んで働けるようにすることが企業の努力義務になります。
少子化対策 強化へ
少子化対策の強化に向けて、去年成立した改正子ども・子育て支援法が4月1日から一部、施行されます。
妊娠・出産支援では、
●妊婦として認定を受けると5万円
●その後妊娠している子どもの人数を届け出ると1人あたり5万円
が支給されます。
働きながら育児をする人を支援しようと、新たに国の2つの給付金制度も始まります。
「出生後休業支援給付金」…夫婦がどちらとも14日以上の育児休業を取得した場合、最長28日間、2人とも手取りの収入が実質的に減らないよう従来からの「育児休業給付金」などに上乗せ
「育児時短就業給付金」…2歳未満の子どもを育てるため、時短勤務をする人のうち一定の要件を満たした場合、賃金の10%相当が支給
年金や医療制度 変更も
年金や医療など、社会保障の制度も変更されます。
このうち公的年金の支給額は、この4月分から、前の年度より1.9%引き上げられます。
ただ、賃金の上昇率よりは低く抑える措置がとられたため、実質的には目減りに。
一方、公的医療保険では、75歳以上の高齢者のうち、比較的収入が多い人の保険料負担が増えます。
国の雇用保険の失業給付では、会社などを自己都合で退職した人は、原則2か月間は受け取れませんでしたが、その期間が1か月間に短縮されます。
安心して転職活動が出来る環境を整えることがねらいです。
2025年3月31日をもって高年齢者雇用安定法の経過措置が終了し、希望者全員の65歳までの雇用確保が適用されます。
これまでは、2013年3月31日までに労使協定を結んだ企業に限り、継続雇用の対象者を限定できる特例が認められていました。
2025年4月1日以降は、すべての事業主は希望する高年齢者を継続雇用しなければなりません。
企業は新しいルールに対応できるよう、早めの準備が求められます。
車検の受けられる期間の変更
2025年4月より車検制度が改正され、車検を受けられる期間が従来よりも長くなります。
これまでは「車検証の有効期間満了日の1ヶ月か月前から満了日まで」と定められていましたが、新制度では「2ヶ月前から満了日まで」と、これまでより1ヶ月延長され、ユーザーはより余裕を持って受検できるようになりました。
以前から有効期間満了日の1ヶ月前よりも前から車検を受けることは可能でしたが、そうすると車検満了日までもが早まってしまうというデメリットがありました。
この変更により、年度末など特定の時期に車検が集中するという問題の緩和が期待されています。
これにより、ユーザーは満了日にこだわることなく余裕を持って車検を受けることが可能となり、整備工場の混雑緩和にもつながると期待されています。
マイナ免許証 開始!
マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)
マイナ免許証とは
マイナ免許証とは、免許情報が記録されたマイナンバーカードのことです。
道路交通法の改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、3月24日から全国で「マイナ免許証」の運用が開始しました。
希望する場合は、運転免許証に代わり「マイナ免許証」を所有することが可能です。
運転免許証の持ち方
今後、運転免許証は3つの持ち方が可能です。
マイナンバーカードに記載される情報
マイナ免許証のICチップには、以下のような情報が記録されます。
マイナ免許証のメリット
マイナ免許証を取得することで、以下のようなメリットがあります。
マイナ免許証のみを保有する場合は、住所変更などのワンストップサービスを利用することで、氏名・住所・生年月日を変更する際に、市区町村での手続きのみで完了できます。
警察署や免許センターへの届け出は不要です。
また、免許更新時の講習もオンラインで受講できたり、手数料が安くなるなどのメリットがあります。
詳しくは、警察庁「マイナンバーカードと運転免許証の一体化」をご確認ください。
運転免許証の更新
免許証更新時に、オンライン講習を受講したい場合は、事前にマイナ免許証を取得する必要があります。
マイナ免許証の更新方法の詳細については、最寄りの警察署や運転免許センターなどの詳細情報をご確認ください。
免許更新時にマイナ免許証を取得すれば手数料は無料ですが、免許更新時以外で取得すると1,500円の手数料がかかります。
従来の運転免許証の更新手続きや適性検査、高齢者の更新手続きなどについては、以下をご確認ください。
運転免許証(更新、再交付、返納について)
※高齢者講習対象者(更新期間満了日年齢が70歳以上の方)は、オンライン講習の対象外です。
★今後も色々と変わっていく事柄があるようです。
たまには良いニュースもありますので、こまめにチェックしていきましょう!!
新生活が始まる前に知っておきたいこと
/カテゴリ: 情報4月から就職や転勤、入学など、新生活が始まるという方も多いのではないでしょうか。
それに伴い、引っ越しをする、自転車に乗るようになる、という方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、地震についてと、自転車の交通ルールについてお伝えしたいと思います。
●大震災から〇〇年、地震保険をかけているのは…?
まず地震についてです。
今年、阪神淡路大震災から30年、東日本大震災から14年が経ちました。
阪神淡路大震災が起こる前、地震保険をかけている世帯は約7%だったのが、
現在は35.1%に上がりました。(共済は含めず)
これって高いと思いますか?
確かに7%に比べると増えたようには感じますが、半数以上の方がまだ加入されていないのです。
被災された方は、まさか自分が住んでいるところが…と口をそろえて言われるようです。
こちらでは何度もお伝えしていますが、地震が原因の損害は「火災保険」では補償されませんので、「地震保険」が必要です。
未加入の方は、検討してみてはいかがでしょうか?
賃貸物件の場合、家財のみの火災保険となる場合が大半ですが、大切な家財を地震から守るためにも家財の地震保険加入をおすすめします!
●知っているようで知らない?自転車の交通ルール
続いては自転車の交通ルールについてです。
前回のお金の勉強会のブログで「自転車の酒気帯び運転で免許停止になる」という話題を投稿したあと、
スタッフ間やお客様から、自転車の交通ルールを知っているようで知らないというお話が出ました。
自転車の運転には運転免許が必要ないものの、道路交通法上、軽車両とみなされ、車両の一種です。
自転車を押して歩いている時には歩行者とみなされますが、搭乗中は車の仲間ということで、
自動車と同じように道路交通法で定められるさまざまな交通ルールがあり、どのような交通ルールがあるのかを熟知した上で、運転する必要があります。
●あまり知られていない自転車事故の現状
実は、自転車関連の事故はここ数年は増加しています。
死者や重傷者がでるような大きな事故の半数以上は、明るい昼間に起きており、自転車に乗り始めて間もない子供より、20歳代以上の事故が多いことから、交通ルールを忘れてしまっている、あるいは、交通ルールが変更されていることを認識していない可能性があります。
大きな事故の相手は自動車であることが多く、そのうち半数以上が出会い頭に起きています。
このような事故では、安全不確認や一時不停止など、自転車側にも交通ルール違反が多いことが分かっています。
交通事故の加害者や被害者にならないことはもちろん、安全で快適に自転車を利用するために、今一度、自転車の交通ルールを確認してみましょう。
●自転車の交通ルール① 道路標識
警察では、大きな事故に直結する信号無視、一時不停止、右側通行、歩道の通行方法などの危険な違反に重点をおいた指導警告、取締りを強化しています。
車では当然のことですが、自転車でも、信号はもちろんのこと、道路標識等の指示にも従わなければいけません。
【主な道路標識】
一時停止
一時停止のための停止線があればそこに(なければ交差点の手前に)一時停止し、左右の安全を確認してから進みます。
※徐行(直ちに停止することができるような速度で進行する)ではなく、一時停止する必要があります。
一方通行
この標識のある道路では、矢印と反対の方向へ走行してはいけません。
一方通行の標識の下に、「自転車を除く」と明記されている場合は、自転車は通行可能です。
車両進入禁止
一方通行の道路で、逆走することになる方向へ車両の進入を禁止している標識であり、自転車にも適用されます。
車両進入禁止の標識の下に、「自転車を除く」と明記されている場合は、自転車は進入可能です。
どれも見覚えのある標識ですが、自転車に乗る時に確認して守っていますか?
守らねばならない道路標識が、この他にもたくさんあります。今一度、ご確認ください。
●自転車の交通ルール② 左側通行
自転車は車道の左側を通行することになっています。
安全な通行を促すため、主に車道の左側端に自転車ナビマーク、交差点に自転車ナビラインの設置を推進しています。
通行すべき部分、進行すべき方向を明示するもので、逆行はできません。
通行方法については、法定又は道路標識等の交通規制に従ってください
●自転車の交通ルール③ 歩行者優先
歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
例外的に歩道を通行する場合は、歩行者を優先してください。
普通自転車等及び歩行者等専用(普通自転車歩道通行可を示す道路標識)
普通自転車歩道通行可を示す道路標識等がある場合や、車道の状況等に照らして車道の通行が危険な場合などは、歩道を通ることができます。
しかし歩道を通るときは、歩行者優先です。ゆっくり通行し、歩行者の通行の妨げになるときは一時停止してください。
しかし歩道を通るときは、歩行者優先です。ゆっくり通行し、歩行者の通行の妨げになるときは一時停止してください。
自転車のベルは、自動車の警音器(クラクション)にあたります。
むやみやたらに鳴らすことは道路交通法第54条第2項に抵触しますので、気を付けましょう。
●このほかにも、新生活に見直すべきことはたくさん!
家族構成や、生活スタイルが変わることで、加入中の保険の補償内容を見直した方が良い場合もあります。
補償内容を忘れてしまったり、再度確認したいという方は、ぜひ弊社へご相談ください!
【お金の勉強会】自転車の酒気帯び運転で運転免許停止!?
/カテゴリ: お知らせ最近、性加害事件や、道路陥没事故など、様々な事件や事故が後を絶ちません。
つい先日、福山市では誤ってNTT西日本の通信ケーブルを切断し、一部エリアで固定電話回線やインターネット回線が利用できなくなる事故もありました。
広島市では去年9月に引き続き道路陥没事故が起こりましたね。
さて、その中でも、驚きのニュースが飛び込んできたので、皆さまにご紹介します。
●自転車の飲酒運転
飲酒運転はダメ!ということはもう当たり前に周知のことですが、去年11月に、自転車での酒気帯び運転が新たに罰則の対象となりました。
自転車での酒気帯び運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則です。
そんな中、去年大阪で自転車による酒気帯び運転をした男性に対し、6ヶ月以内の運転免許停止の行政処分が下されました。
警察は、男性の行為が道路交通上で著しい危険を生じさせる状態にあったと判断。
また、将来的に自動車での飲酒運転等により交通事故を引き起こす恐れがあるとしました。
自転車の酒気帯び運転による免許停止処分は、大阪府内で初めての事例となりました。
自転車の飲酒運転で免許停止処分となる可能性があることを、初めて知った方も多いのではないでしょうか。
自転車は免許不要で手軽に乗れること、人力での走行という特性から「危険性が低い」と誤って認識されがちですが、自転車による交通事故は後を絶たず、死亡事故も発生しています。
飲酒運転は、車両の大小や動力の有無に関わらず、重大事故につながる危険性があります。
●飲酒運転と保険
ところで、飲酒運転は保険にどう関わってくるかご存じですか?
保険種類別にみていきましょう。
★自動車保険
・対人賠償責任保険、対物賠償責任保険
(他人を死傷させた、あるいは他人の財物に損害を与えた、といった場合に使える補償)
飲酒運転をして、他人を死傷・財物に損害、という場合、被害者救済の措置から、保険金は支払われます。
(ただし、今後の保険継続は難しい可能性も…)
・人身傷害保険、搭乗者傷害保険など
(運転していた自分や、同乗者が死傷した場合に使える補償)
飲酒運転によるものだと、こちらの保険金は支払われません。
補償の範囲を搭乗中限定にしていなければ、自転車に乗っている時も対象となりますので、自転車の場合も保険金は支払われません。
加えて、運転者はもちろん、
・運転者が飲酒することをわかっていて運転者に車(自転車を含む)を貸した人
・運転者に酒類を提供した人
・飲酒運転であることをわかっていて運転者の車(自転車を含む)に同乗した人
にも処罰が与えられます。
★医療保険や死亡保険(終身保険・定期保険・収入保障保険など)
こちらも同様に、保険金が支払われない事由に含まれています。
★健康保険
飲酒運転でケガをして病院に入院したり通院した場合、健康保険が使えません!
つまり、治療費は全額自己負担となります。
そして、仕事を休んでも傷病手当金も支給されません!
まさに、百害あって一利なし!!!
社会規範はどんどん厳しくなってきますが、相変わらず自動車の無保険車も存在します。
自転車保険(個人賠償責任保険)に関しては、各都道府県によって違いますが、広島県では加入の義務化がされています!
加害者にも被害者にもなりたくないですよね。
ひとりひとりがルールを守るという意識を高く持って、自分だけでなく他人のためをも思える優しい世の中になるといいですよね🥰
保険の補償内容を確認したい方はこちら↓
全国版女性ファッション誌『CLASSY.(クラッシー)』に掲載されました!
/カテゴリ: お知らせこの度、全国版女性ファッション誌『CLASSY.(クラッシー)』3月号(2025年1月28日発売)の
「困った時に頼れる専門家LIST」特集に掲載されました!
マネー・資産形成、相続・終活等のご相談は、ぜひ弊社まで!!
地域情報誌「ぷれすしーど」に掲載されました!
/カテゴリ: お知らせぷれすしーど第855号(1月17日発行)の「異業種リレーのわ」に掲載されました。
今後とも弊社をよろしくお願いいたします。
こちらの記事が載ったバックナンバーはこちらをクリック!